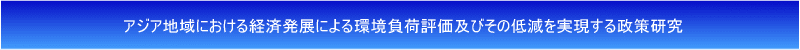- 小谷真吾 「ブタはどのようにして現金になりうるのか?-パプアニューギニア高地辺縁部における生業生態と貨幣経済」,『国立歴史民俗博物館研究報告』,2005,123:85-102.
- Tanaka, M.,Umezaki, M.,Natsuhara, K.,Yamauchi, T.,Inaoka, T.,Hongo, T.,Nagano, M.,Watanabe, C. and Ohtsuka, R. No Difference in Serum Leptin Concentrations between Urban-Dwelling Austronesians and Non-Austronesians in Papua New Guinea.American Journal of Human Biology. 2005, 17,696−703.
- 小谷真吾 「バナナとサツマイモ ―パプアニューギニアにおける生業変化の事例―」,『歴史評論』,2004,650: 40-54.
- 小谷真吾 「ジェンダーと兄弟姉妹関係 -パプアニューギニアにおける女児死亡の事例を基に-」,『国立歴史民俗博物館研究報告』,2004,109:
293-319.
- Umezaki, M. and Ohtsuka, R. Adaptive strategies of Highlands-origin migrant settlers in Port Moresby, Papua New Guinea. Human Ecology, 2003, 31: 3-25.
- Odani, S. Individual Variations in Fishing Activity with Respect to Household Food Consumption Pattern on Pam Island, Papua New Guinea. Anthropological Science, 2003, 111: 383-387.
- Odani, S., Subsistence ecology of the slash and mulch cultivating method:
empirical study in Great Papuan Plateau of Papua New Guinea. People and
Culture in Oceania, 2002, 18: 45-63.
- Umezaki, M. and Ohtsuka, R. Changing migration patterns of the Huli in Papua New Guinea Highlands: A genealogical-demographic analysis. Mountain Research and Development, 2002, 22: 256-262.
- 大塚柳太郎(編著),須田一弘・梅崎昌裕・稲岡司ほか(著)『ニューギニア:交錯する伝統と近代』,京都大学出版会,2002年,京都.
- 小谷真吾 「パプアニューギニア高地辺縁部における伝統的農法の生業生態と社会構造」,『動物考古学』,2001,17:25-49.
- Umezaki, M., Natsuhara, K., and Ohtsuka, R. Protein content and amino acid scores of sweet potatoes in Papua New Guinea Highlands. Ecology of Food and Nutrition, 2001, 40: 471-480.
- Yamauchi, T., Umezaki, M., and Ohtsuka, R. Physical activity and subsistence pattern of the Huli, a Papua New Guinea Highland population. American Journal of Physical Anthropology, 2001, 114: 258-268
- Yamauchi, T., Umezaki, M., and Ohtsuka, R. Influence of urbanisation on physical activity and dietary changes in Huli-speaking population: a comparative study of village dwellers and migrants in urban settlements. British Journal of Nutrition, 2001, 85: 65-73
- Natsuhara, K., Inaoka, T., Umezaki, M.,Yamauchi, T., Hongo, T., Nagano, M. and Ohtsuka R. Cardiovascular Risk Factorsof Migrants in Port Moresbyfrom the Highlandsand sland Villages,Papua New Guinea. American Journal of HumanBiology. 2000, 12, 655-664.
- Umezaki, M., Kuchikura, Y., Yamauchi, T., and Ohtsuka, R. Impact of population pressure on food production: an analysis of land use change and subsistence pattern in the Tari basin in Papua New Guinea Highlands. Human Ecology, 2000, 28: 359-381.
- Natsuhara, K. and Ohtsuka, R. Nutritional Ecology of aModernizing Rural Community in Papua New Guinea: An Assessment from Urinalysis. Man and Culture inOceania. 1999, 15, 91-111.
- Umezaki, M., Yamauchi, T., and Ohtsuka, R. Diet among the Huli in Papua New Guinea Highlands when they were influenced by the extended rainy period. Ecology of Food and Nutrition, 1999, 37: 409-427.
- Suda, K. Dietary change among the Kubo of WesternProvince, Papua New Guinea, between 1988 and 1994. Man and Culture, 1997,13: 83-98.
- Suda, K. Time allocation and food consumption among the Kiwai-speak ing Papuan in Papua New Guinea. Senri Ethnological Studies,1996,42: 89-104.
- 須田一弘 「文明がやってきた−パプアニューギニア・クボの場合」,『北海学園大学人文論集』,1996,6:153-166.
- 須田一弘 「パプアニューギニア・クボ族のサゴ作り生産性について」,Sago Palm,1995,3:1-7.
- 須田一弘 「パプアニューギニア・キワイ漁民の時間利用と食物摂取」,『北海学園大学人文論集』,1993,1:53-78
- Suda, K. Socioeconomic changes of production and consumption in Papua New Guinea societies. Man and Culture in Oceania, 1993, 9: 69-79.
- Suda, K. Leveling Mechanisms in a recently relocated Kubor village, Papua New Guinea: a sociobe-havioral analysis of sago-making. Man and Culture in Oceania, 1990, 6: 99-112.
|