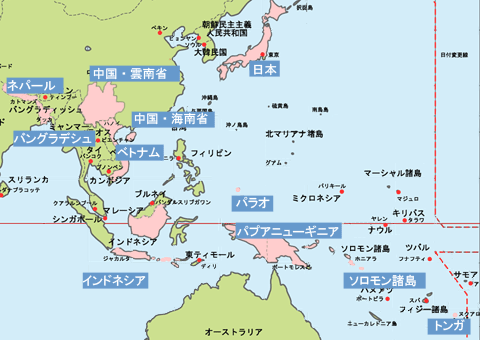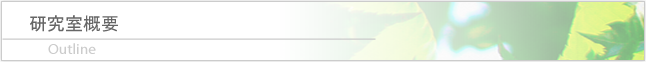
人類生態学では,環境保健学的な課題,ヒト個体群生態学的な課題,あるいはその両方にまたがる課題を扱い, 目的に応じてフィールドワーク, 実験を行っている.フィールドは,アジア・オセアニアの主として農村部であり,人口・栄養/成長・環境を重視した研究を行った.実験では, 胎生期における重金属などへの曝露が生体に及ぼす影響について,これを修飾する要因に着目して解析した.過去2年度の間に実施された, あるいは引き続き継続中の主要なプロジェクトは以下の通り.
1.周生期における化学物質の発達神経毒性
2.発展途上国における水・大気環境と健康の問題
3.発展途上国における栄養・成長・身体活動に関する研究
4.開発と生業,生業転換と適応
5.国内における研究―魚などに含まれるメチル水銀とセレン
人類生態学教室の主な調査地
(タイトルをクリックすると各説明の先頭に飛びます)
1.周生期における化学物質の発達神経毒性:
現代の人類は産業社会であるか否かにかかわらず,極めて多種の化学物質を生活に使用し,これらの化学物質に曝露されている. こうした化学物質は,現代の人間にとって重要な環境要因となっている.化学物質に対する感受性が高い場合が多いとされる周生期の曝露が, 出生後に及ぼす影響に着目した研究を行った.複数の国内研究機関との共同研究により,微量曝露が現在のわが国でも問題となっている重金属 (水銀・カドミウム),ならびにいわゆる内分泌かく乱化学物質に焦点をあて,行動機能から遺伝子発現まで,個体あるいは細胞を用いて, 多層的に影響を検索する実験的研究を実施し,メタロチオネインによる発達毒性の修飾,微量カドミウムによる発達神経毒性発現の 可能性を示した. また,フィールド調査で得られた知見に基づき,砒素と必須微量栄養素(セレン)欠乏との周生期における相互作用を検討し, 甲状腺ホルモン環境への影響,体内動態における両者の相互作用を報告した.
2.発展途上国における水・大気環境と健康の問題:
アジア・ラテンアメリカ諸国を中心に多くの途上国では,飲料水として用いる地下水の汚染が問題となっている. これまでバングラデシュで起こった大規模な砒素による地下水汚染の健康影響について調査を行ってきたが, 同じ水系にあるネパールで調査を実施, 国外の共同研究者の協力を得て,特に栄養状態との関連について検討を行った.バングラデシュの調査で示された性差を確認するとともに, 低栄養状態と砒素毒性とが相互に増悪しあうという関係を見出した.インドネシアでは,水質,特に農薬・金属・生活排水のもたらす 複合的汚染が健康に及ぼす影響についての調査に着手した.その背景となる水質調査を海外の研究機関と共同で実施し,実態を報告した. 水質問題とともに大気汚染の問題もアジアの都市部では深刻である.インドネシア都市部における鉛汚染の実態について調査を行い, 鉄栄養が鉛の体内負荷の修飾要因になる可能性を示した.
3.発展途上国における栄養・成長・身体活動に関する研究 :
バングラデシュ農村部において,食物摂取,栄養状態ならびに活動状態の性差について検討し,食物摂取に関して,女性が男性に比較して 不利な状況にあることを示した.インドネシア農村部において思春期前の栄養状態と出生時の諸要因との関係について解析した. また,肥満の率が高いトンガにおいて,思春期女子の身体計測を行い,肥満に寄与する要因を検討した.中国の農村部学童における 住血吸虫症感染の実態を調査し,感染と栄養状態とが,それぞれ小児の成長に及ぼす影響について相対的な重要性を評価した. 活動とエネルギー代謝は,人類生態学的観点]からも,途上国にも拡大しつつある生活習慣病の問題に取り組む観点からも重要な要因である. 主として,生活活動の中でのエネルギー代謝を重視した 研究を行ってきたが,パプアニューギニアにおける身体活動が,農村から都市への移住にともなってどのような変化をきたすかを解析した. また,特殊な例として相撲力士のエネルギー代謝の検討を行った.
4.開発と生業,生業転換と適応:
アジア・太平洋地域の多くの国では,経済発展・資源獲得・観光など多様な目的のもとに開発事業が実施され,これにともなって住民の生業・ 資源・生態系は大きな外力を受けて変化を起こし,住民の生活・栄養あるいは健康の状態,疾病構造などを変えつつある.このような開発と 住民の生活との関連について,中国ならびにソロモン諸島において調査を行なった.中国では生業転換が実際に起こるプロセスを世帯レベルの 違いに焦点をあて,世帯レベルでの適応戦略の決定要因の同定を試みた.なお,生業転換と土地利用の関連を解析するため, GIS(地理情報システム)/GPSを応用した.
5.国内における研究―魚などに含まれるメチル水銀とセレン:
水銀セレン調査 (リンクをクリックして下さい)
人類生態学教室の主な調査地